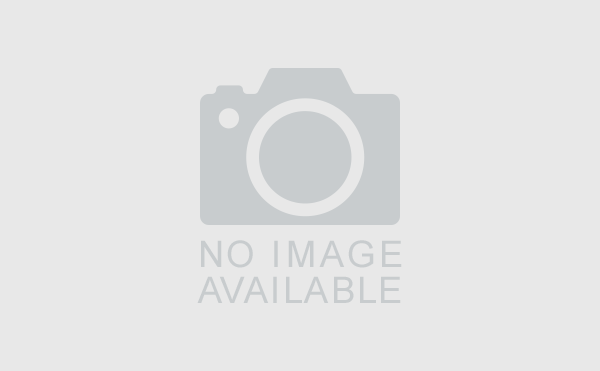第52話「黒地に白の水玉模様の羽、カノコガ」
みなさんこんにちは!ヨッしぃです!
今回はカノコガをご紹介いたします。

初夏の日中、山の近くを歩いていると、ヒラヒラと小さな昆虫が飛んでいることがあります。ヒラヒラと飛ぶ昆虫はよくいますが、胴体が黒とオレンジ、羽の色が黒地に白の水玉。
カノコガです。

夜行性のガが多い中、カノコガは日中も活動するガの仲間で、成虫は花の蜜などを吸います。
比較的細めの黒い羽には白の水玉模様が。おそらく、これがカノコ(鹿の子)模様なのだろうと、容易に推測できますね。




あまり昆虫に詳しくない人が見るとガの仲間とは思わないかもしれません。どちらかといえばハチ?の仲間に似ていますよね。
そうなんです、フタオビドロバチというハチに擬態している言われているんです。毒があったり、自分より強い生き物に擬態するというのもよくあるパターンですね。
フタオビドロバチによく似たハチの仲間?を見つけたので一応載せておきます。多分別の種だと思うんですがよくわかりません。
とりあえず似ているので、あくまでイメージとして。



羽を触ると、そのままの模様の鱗粉が、まるでハンコを押したように指に写ってしまうことからハンコチョウとも呼ばれるらしいですが、もうそうなるとガなのか、チョウなのか、ハチなのか、ますます分からなくなってきそうですね(笑)
ちなみに、時期を同じくしてヒラヒラと舞い飛ぶ別のガ、ウメエダシャクも黒い羽に白い斑点のある、日中に飛ぶガの一種で、パッと見た感じは非常によく似てます。
○カノコガは体のオレンジ部分より黒色部分のほうが多い、ウメエダシャクはオレンジの部分が多く黒とオレンジの縞の数が多い
○カノコガの羽の模様は単純な水玉模様(鹿の子模様)、ウメエダシャクは複雑な斑紋
○カノコガの幼虫はケムシ、ウメエダシャクの幼虫は毛の無いシャクトリムシ
というような外見の違いがあり、分類上も全く別種のガになります。


よく似ていますね!
〈カノコガのまとめ〉
○大きさ:開帳30〜35ミリ
○成虫出現時期:6-8月頃
○分布:北海道・本州・四国・九州
○生息地:山地、開けた草原など
○食性:幼虫は毛虫でシロツメグサを食べる、成虫は花の蜜などを吸う
というわけで、今回はカノコガをご紹介いたしました!
というわけで、皆さんまたお会いしましょう!